こんにちはさかもとです。
早速ですが、ご家族や支援者として認知症の方々と接するときに「どう関わればよいか」悩んだり、困ったりしたことがありませんか?
実はその悩みこそが大正解なのです。
なぜなら、非薬物療法では認知症ケアにおいて一番大切なことは「関わり方」と言われているからです。
本ブログでは‘‘適切な関わり方‘‘について簡単に解説していきます。
1.認知症を持つ人を考えるうえでまず大切にしてほしいこと
さて、この記事を読んでくださっている皆様は認知症を持つ人について考えてくださっている人がほとんどだと思います。
その際に「認知症ってどんな症状なんだろう?」「認知症だからこういう行動をしてしまうんだ」と考えることも多かったのではないでしょうか。
その考え方も間違ってはいません。
しかし、認知症ケアの観点から大切にしていただきたいのは「【認知症】を持つ人」ではなく、「認知症を持つ【人】」ということです。
そう、つまり「認知症」という状態ではなく「その人個人」にフォーカスして考えてほしいのです。
2.その人個人を考えるとは
では、その人個人とは、どう考えたらいいのでしょうか。我々が人間関係を広げていく時と同様で、その人の特性に興味を持ち、知り、理解する必要があります。
・性格
・問題への対処方法
・生活歴・生きた歴史
・健康状態
・人間関係
パッと思いつくだけでもこれだけ個性がありますね。
例えば、食卓で野菜を最後まで残しておく人がいるとしましょう。
その人の個性を理解していないと「野菜が好きだから野菜を取っておいている」のか「野菜が嫌いで食べたくないから残している」のかがわからないわけです。
つまり、個性によって同じ行動でも理由が違うわけです。
そのため、その人の個性について理解をしておく必要があります。
3.一番適切な関わり方とは何か
前述のとおり、同じ行動でも個人によってその行動の理由が違うのであればもちろん適切な声のかけ方も変わってくるわけです。
しかし、共通して一番大切な関わり方があります。それは「共感的理解」です。
その方のその行動、その理由をその方の歩まれた人生に照らし合わせながら理解し共感する、そして共に行動したりすることがその方の考えや行動を認めることとなり一番大事だといえるのです。
4.やってはいけないこと・やらないでほしいことをしてしまった時
では、きっとこんな疑問が出てくるでしょう。「やってはいけないことや、やらないでほしいことをしてしまった場合も共感するの?」
結論から言うと「yes」です。
もちろん、やらないでほしいことをやり続けてもいい、という意味ではありません。
大事なのはその考え・行動を理解することです。そのうえで適切な対応をすることが大切です。
例えば、床にテーブルのお茶をばら撒いてしまう方がいるとしましょう。まずこの時点で「ばら撒いてはいけません」と注意するようではもちろんナンセンスです。
理由を聞くと「床に虫がいた」と言ったとします。まずこれを認めてあげることが大切です。
対応の仕方は様々ありますが、僕なら
・「大丈夫でしたか?もうどこかに行きましたか?」
・「その虫はあなたに何か悪さをしませんでしたか?」
などと聞くと思います。
そのあとに、「床に水をまいてしまうとお掃除が大変なので、次からは人を呼ぶようにしましょうね」などと対応するかと思います。
こういった本来ならやってほしくない行動に対しても共感的理解を示すことによって存在を認めることができ、認知症を持つ方々に「やすらぎ」や「おちつき」を与えることができます。
5.まとめ
認知症を持つ方々と関わる際に、適切なコミュニケーションは必要不可欠です。個人個人の生きた歴史にフォーカスした共感的理解を意識するだけで認知症を持つ方々のやすらぎや落ち着きにつながっていきます。ぜひ試してみてください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
ご質問・ご相談がある方はこちらのお問い合わせページからお気軽にどうぞ

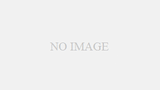
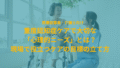
コメント