ご覧になっていただきありがとうございます。さかもとです。今回は医療従事者や介護士など向けの記事となっています。
皆様は重度認知症を持つ方々にこんな悩みを持った経験はないでしょうか。
「本人の意思がわからないから何を目的にケアをしたらいいかわからない…」
本記事ではそんな悩みを持つ方に向けて現場ですぐに実践できるケアの考え方をまとめました。
1.重度認知症を持つ方々と関わる上で理解すべきこと
さて、現場で働いている皆様は重度認知症を持つ方について冒頭の悩みについて一度は考えたことがあると思います。
その理由は重度認知症を持つ方々は身体機能の大幅な向上がみられにくい上に、ご自身の生活歴やご自身の正確なHOPEを話すことが困難なため、その方の為のその方に合わせた認知症ケアや目標を考えることが難しくなってしまうからだと思います。
つまり、「表出」する機能が損なわれてしまっているのです。
しかし、表出が困難であっても「感情」が失われているわけではありません。
そのため重度認知症の方々に対しては「心理的ニーズ」を満たしてあげることが特に重要となるのです。
2.重度認知症ケアにおける心理的ニーズとは何か
今回のキーワードは「心理的ニーズ」です。
心理的ニーズとは簡単に言うと、「人間であれば誰しもが生まれながらに持っている心理的な欲求」のことです。
つまり、自分の意思を表出することが困難な重度認知症を持つ方々でも心理的ニーズはあり、それを持ている以上、「一人の人間として無条件に尊重され、尊厳が保たれている」必要があるのです。
心理的ニーズを理解する上で重要なのは
・自分らしさ
・愛着・結びつき
・たずさわること
・共にあること
・くつろぎ・やすらぎ
だとトム・キットウッド氏は提唱しており、その中心には「愛」があると説明しています。
次項からはそれぞれについて具体例を交えつつ解説していきます。
3.心理的ニーズ「自分らしさ」
まずは「自分らしさ(アイデンティティ)」です。
自分の生き様や生き方そのもので、どんな状態であっても「自分らしく暮らし続けたい」という願いのことです。
その方の生きた歴史や生活習慣をご家族等から聴取することによってその方が大切にしていた世界に触れ、その方なり、その人ならではの暮らし方を尊重したケアが大切ということです。
例えば、現場に時には、子ども扱いしているかのような口調で重度認知症の方々と話すスタッフを見受けることがあります。これはその人らしさを尊重していないということになるのです。
その方を尊敬し、受け容れ、喜び合うことが「その人らしさ」考えるうえでのキーワードとなります。
4.心理的ニーズ「愛着・結びつき」
次に「愛着・結びつき」です。
これは少々難しいですが、一般的な古いもの(その方の世代に流行した駄菓子や音楽等)ではなく、理屈では説明がつかないどうしようもなく好きなものやなんとなく落ち着くものを指します。これは、家族や友人等のとの親しい人との結びつきを持ち続けたいという願いも含まれます。
例えば、物で言えば、昔からご本人が使っている寝具や食器、お気に入りのラジオ等が含まれるかと思います。
重度認知症の方の中でもなかなか寝つけない方やずっとソワソワしている方はよくいられると思います。そういった方々は家族や友人が来た際はどんな様子かみてみてください。
意外にも、落ち着いている方が多くいらっしゃるのではないでしょうか。
それと同様にご家族等の親しい方にその方が愛着を持っていたものを持参していただくだけでご本人の心理的ニーズがまた一つ満たされ、落ち着きを得られることがあります。
また自分たちも誠実に、共感をもってわかろうとすることでお互いに結びつきを感じて過ごすことができます。
5.心理的ニーズ「たずさわること」
続いて、「たずさわること」です。
これは、人間は誰しも、誰かの役に立ちたいという願いを持っているということです。
認知症の方でも、「できること」と「豊かな感性」は残っています。認知症ケアにたずさわる私たちは「できなくなったこと」ではなく「できること」に目を向けて役割の持てる場面を作ることが重要です。
そして、その成果を褒めること、感謝の意を伝えることがとても重要です。
人間にとって一番の恐怖とは「誰からも必要とされなくなること」なのです。
役割を与えることはその人の能力・気力を引き出すことにつながります。
6.心理的ニーズ「共にあること」
「共にあること」に関しては前述の「結びつき」や「たずさわること」少し似ています。
どのような人も「人とつながりを持って生きていきたい」「社会とつながっていきたい」という気持ちです。
例えば、重度認知症の方と関わる職業に従事していればその方についての話をスタッフ間ですることもあるでしょう。
その際、その方の傍らに立ち、スタッフ間で話すという行為がしばしばあると思います。
しかしそれはは「無視をしている」「いないものとして扱っている」ということになってしまいます。
本人についての話は、その方を挟んで「本人がいる」という当たり前のことを大切にし、一員として、個性・存在を感じられるようにしなければなりません。
7.心理的ニーズ「くつろぎ・やすらぎ」
「くつろぎ・やすらぎ」とは不安や混乱、緊張がなく、心穏やかにリラックスしている状態のことです。
例えば、特に病院や施設の中では穏やかさがなく、不安や混乱が大きい方が多くいると思います。
その中で、後回しにすることなく思いやり(やさしさや温かさ)を持って接したり、トイレやお着換え等の介助時にも急かすことなくリラックスできるペースで行うことで、不安や混乱なく、リラックスした環境で過ごすことができると思います。
8.重度認知症ケアの目標設定において大事なこと
今回は、「心理的ニーズ」について話させていただきました。
これら「心理的ニーズ」は私たちは自分で満たすことができますが、「身体」や「表出」する機能が損なわれた重度認知症を持つ方々はご自身で満たすことができない状態です。
そのため、私たちがこれらの「心理的ニーズ」を満たしてあげる必要があるのです。
また、それが重度認知症を持つ方々へのケアや目標設定の方向性になるのではないかと私は日々考えております。
また、「認知症ケアにおける関わり方の基本」も知っておくとより理解が深まります。
最後までお読みいただきありがとうございました。
ご質問・ご相談がある方はこちらのお問い合わせページからお気軽にどうぞ
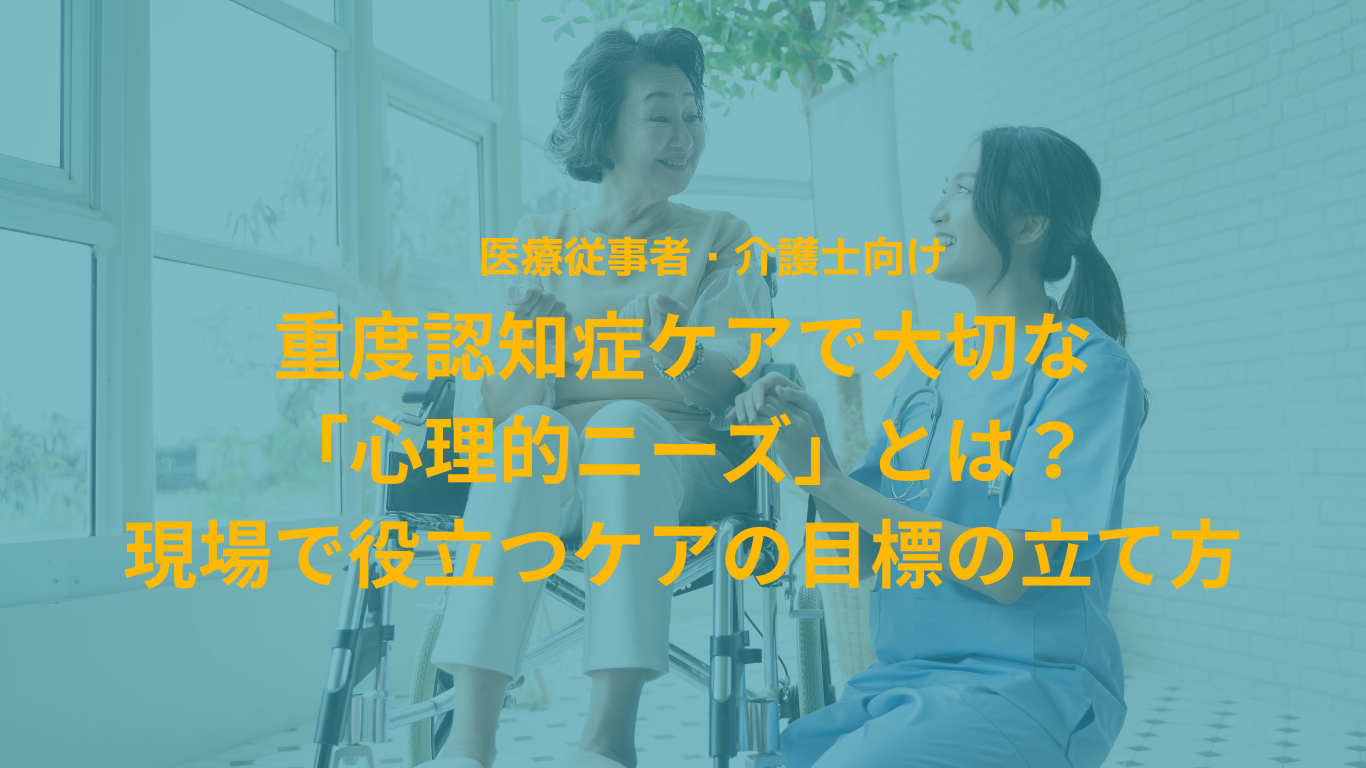
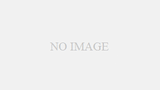
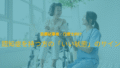
コメント